セミナー詳細

栄養療法を実践するためには、基本的な分子栄養学の理解に加えて、次の能力が必要です。
- 患者を診て、「この人には分子栄養学的な診療が必要かどうか」を見極める能力
- 問診から、 「どのような検査が必要か」を見分ける能力
- 患者さんに、「分子栄養学的な検査治療」を適切に提案する能力
- 検査結果から「分子栄養学的」に体の状態を読み取る能力
- 体の状態から「どのような栄養素をどのように摂取、点滴するのか」を決定する能力
この5つの能力を習得していただくのが本講座の目的です。
そのため、実践編に重点を置いた講座内容の構成になっています。
分子栄養学 基本編
- 分子栄養学の考え方のフレームワークを脳内に構築する方法 ---
※ フレームワークとは、考え方の枠組みの事です
人間は60兆個の細胞から出来ています。細胞の営みを知るのには血液検査が最適です。
まず、体の中を知ることで、そこからどのような治療を組み合わせることも自由です。
① 臓器別医学からの脱却
全身 - 臓器 - 細胞 - 遺伝子
これらの関係性をつかみ、自由に発想する方法
⇒ これにより、内科でも外科でも耳鼻科でも歯科でも眼科でも、常に全身との関係や、臓器を構成する細胞との関係性を考慮しながら栄養療法の治療の組み立てができる
これらの知識をもとに、ダイエット、疲労症候群、低血糖症などへ応用します。
医科・歯科での症例を元に、実際的な対処をシュミレーションしていきます。
② 臓器別 必要な栄養素
③ 細胞の部位別 必要な栄養素
④ 症状 - 必要な栄養素 - 血液検査の所見 を一致させる方法
⑤ 血液検査の読み方トレーニング (症例1-5をもとに)
⑥ 分子栄養学の実践に必要な様々な検査の申し込み方法
その検査をご自分で行っていただき、結果が出た方は月1回の定期勉強会にご参加ください。
特典 栄養療法の雛形セット
問診表:重金属の蓄積、アレルギー、腸内環境、貧血、低血糖、副腎疲労
など多くの兆候が診られる総合的問診表とその解説
説明書:栄養療法、高濃度ビタミンC点滴療法などの説明書
分子栄養学 応用編
- 疾患の根本原因を知る方法 ----
慢性疾患を引き起こしている原因一つ一つについて解説する
① 感染 ウイルス、細菌、真菌の過剰増殖
通常の検査では難しい微量のマイコプラズマ、カンジタを検出する方法、それに対する対処法を具体的に解説します
潜在的な感染症について キャビテーション(NICO)など
② 消化 胃酸分泌不良、消化酵素分泌不全、腸内フローラ不全
これらに対しての様々な問診、検査方法。腸内環境と全身免疫、精神疾患のつながりについて解説
免疫状態を把握する方法
食物アレルギー検査IgGの読み方、対処法、食事指導の方法
腸内環境総合検査の読み方、対処法、対応するサプリメント、抗生剤の処方について
扁桃と腸管の免疫応答、リンパ球のホーミングなど
③ 感情が体に与える影響
低血糖症、ストレスと腸、副腎疲労
④ 有毒物質
重金属の蓄積が体に与える影響、そのしくみ、歯科アマルガムと全身疾患とのかかわり
体内に蓄積している重金属の評価方法
⑤ 食事
食物アレルギー、糖質制限食が有効な人、やってはいけない人を見分ける。
⑥ 甲状腺
通常の検査では検出する事ができない甲状腺機能異常について解説
⑦ 低血糖症
低血糖症のタイプ別、症状、対処法、他の疾患、ホルモン等とのかかわりについて
⑧ ホルモン分泌異常
副腎、甲状腺、卵巣はお互いに密接に関係しあっている。
⑨ 副腎疲労症候群
ストレス、低栄養が原因だが、他疾患が原因で二次的に副腎疲労を症例が増えている
⑩ カンジタ感染
過剰な抗生剤、ステロイド、砂糖の摂取、ストレスとのかかわりが大きい
対処方法について
特典 サプリメントリスト
分子栄養学的な使用に耐えうる実際のメーカー名と推奨サプリメントリスト
購入法、サプリメントの見極め方
※ エビデンスの得られているものを中心にご紹介します。特定の会社のサプリメントを推奨するものではありません。
分子栄養学 実践編
分子栄養学治療も通常の医療と同じく、実際に患者さんに対して実践していく際に求められる能力があります。
それは、
- 患者を診て、「この人には分子栄養学的な診療が必要かどうか」を見極める能力
- 問診から、 「どのような検査が必要か」を見分ける能力
- 患者さんに、「分子栄養学的な検査治療」を適切に提案する能力
- 検査結果から「分子栄養学的」に体の状態を読み取る能力
- 体の状態から、「どのような栄養素をどのように摂取、点滴するのか」を決定する能力
です。
治療の実際は、
①患者さんを診て、分子栄養学的治療が必要かどうかを見極め、
必要な場合、
②どのような検査が必要かを見分け、
③その検査と治療について提案し、
それが受け入れられたら、
④検査を行い、
結果が出たら、
⑤それを適切に説明し、治療につなげていく
という一連の作業が必要になってきます。
通常の講義だけでは、このあたりの微妙なニュアンスが伝わりにくいので、実際の症例を見ながら、この5つの能力を鍛えていきます。
① 基礎編と応用編を組み合わせ、実際の症例を元にどのように診断し、どのような検査を行い、どのように処方するか
(どこの会社のどのサプリメントをどの位の量でどの位の期間投与するのか)、投薬、点滴をどのように組み合わせるのか
② 疲労を起こす様々な疾患の見分け方
慢性疲労症候群 副腎疲労症候群 甲状腺機能低下症 鉄欠乏性貧血 腸内環境悪化 ミトコンドリア病 水銀中毒
これらには、「疲労」という共通した症状があります。
疲労という症状があった場合、どのようなロジックで原因を見分け、これらの疾患に到達するのか
そして、それに対してどのような対処をしていくのか。
③ 医科と歯科の連携の仕方 どのタイミングでどのように相互紹介をおこなうのか
例)
医科 ⇒ 歯科
・水銀アマルガム、その他のメタルがリウマチ、神経疾患、自己免疫病などの原因の一部と想定される場合
・歯周病が糖尿病悪化因子と考えられる場合
例)
歯科 ⇒ 医科
・口腔内乾燥の原因が内科疾患に対する投薬の副作用、自己免疫疾患として起きている場合
・重金属の蓄積が全身症状を起こしていると想定される場合
その他、皆様の症例を持ち寄り、様々なパターンを検討していく検討会を行い、それをまとめたものを書籍化する予定です。
分子栄養学 治療提案編 (8月1日 刊行予定)
分子栄養学が必要な患者さんをどのように集め、どのように検査や治療の提案をするのか。
院内での案内方法から院内掲示板、ホームページの作成方法まで
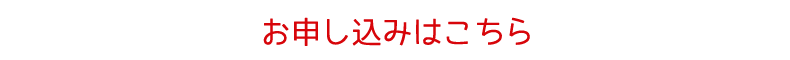
テキスト配信4回、フォローアップメール16回、勉強会4回をすべて含む
受講価格
¥126,000
本講座は終了しました。
最新のセミナー情報はこちら